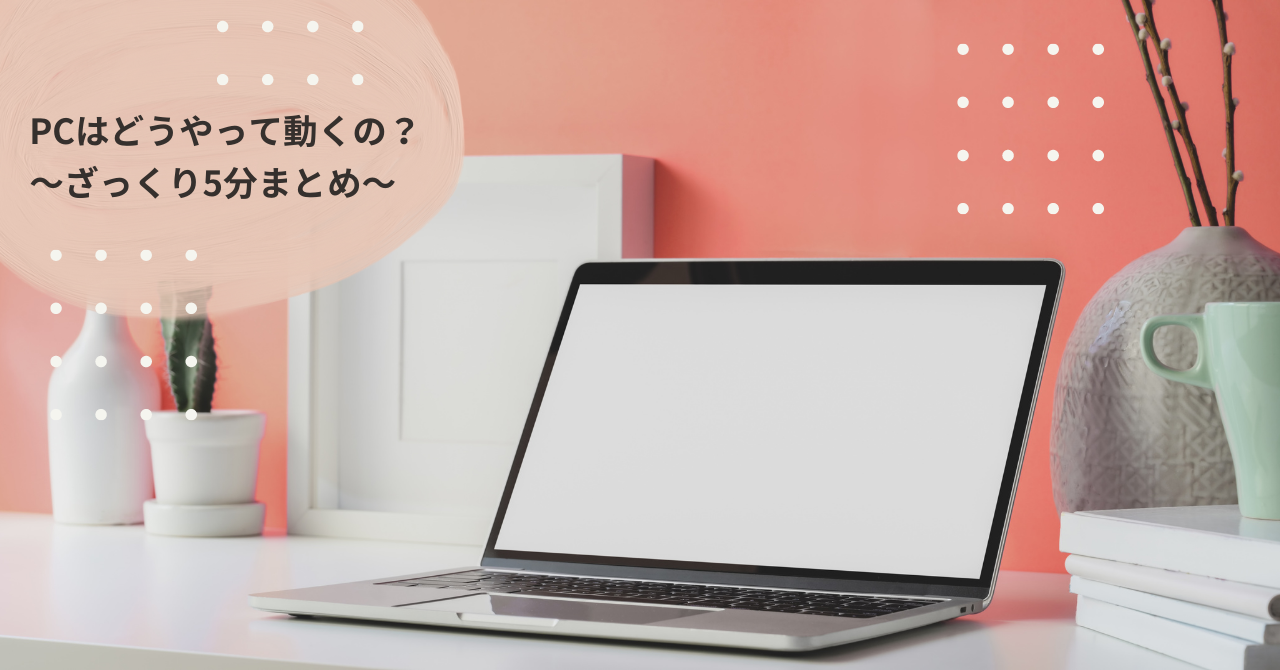現代社会において、パソコンは日用品のひとつです。
一家に一台が当たり前になっているパソコンですが、学校教育でがっつり勉強してこなかった世代には、まだまだ苦手意識を持っている人も多いでしょう。
大人になってからの学び直しは、どうしても独学になってしまいがちです。そうして、多くの人が独学という大海原へ飛び出し、挫折していくのです。
何かに苦手意識を持つ理由は、大抵「前提知識の不足」が原因です。
IT界隈では「知らないことはググれもしない」という皮肉言葉があるように、何をするにも「前提知識」は必要不可欠。大切なのは、「ざっくりでもわかった」という状態になり、最低限の苦手意識を取り除くことでしょう。
まずはPCの動作をざっくり理解することで、最低ラインの苦手意識をなくしていきましょう。

今日はPCについて勉強していくで。
うわぁ、パソコンかぁ。苦手分野です。


なんや、苦手なんかいな。
どの辺が苦手なんや?
なんか、専門用語とかいっぱいあるし。あと、突然不具合起きたりするじゃないですか。そうなったらもうパニック。


確かに。多くの人が苦手意識を持つ理由のひとつやね。苦手意識を持ったままだと、何をするにもマイナスや。苦手意識克服のためにまず大事なのは「好奇心」や。知りたいって思わないことには、メンタルブロックがかかってしまうやろ。
うーん。それはそうなんですけど。
どうしたら好奇心って湧くんですか?


好奇心を持つために必要なのはまず「知識」やな。
知識か。結局勉強なんですね。。


勉強っていうと堅苦しいけどな。「わかった気になる」状態を作るというのが、好奇心をもつ上では大切やで。人を好きになるときも、その人の人となりを知ることは大事やろ。
そう考えたら、そうかぁ。

サッカーを知らない人に、いきなり細かいルールや戦術を学ぼうとしても、挫折してしまいます。
まずは「オフサイドとか戦術とかよくわからんけど、手以外を使ってボールを向こう側のゴールに入れればいいのね!」という状態を作り、実践の中で細かい部分を身につけていくことが良いかと思います。
「とりあえずサッカー知ってるんで、試合はできます」というところまで持っていって、そこから細かい知識やスキルを身につけていくと、サッカーへの興味・関心もグッと高まります。
この記事読んで、PC知識0の人がまず「あー、PCってそうやって動いているのね!」というざっくりした理解を得ていただけますと幸いです。
・PCに命令する
PCは日本語も理解できないし、英語も理解できません。
そしてここも勘違いされる部分なのですが、「プログラミング言語」も、PCは理解できません。では、PCは何語で命令すると動くのでしょうか?
それが「マシン語」です。
マシン語とは「0110001101110111…」こんなやつです。
そう、PCはこの0と1の数字によって動作します。
なぜ0と1でしか動かないのでしょうか?
それは、パソコンが電気信号によって動いているからです。
簡単にいうと、0だと電気信号を流さない、1だと電気信号を流す、ということ。PCの脳みそ的な役割を果たす「CPU」というやつが、0か1かの指令を受け取り電気信号流すことで、PCは動作します。
問題は、0と1で指令を送らないとPCは判断できないということ。
例えば、「今日の天気を調べたい」と思ったときに、それをマシン語(0,1)に変換して指令を出してあげないと、PCは動きません。だけど、マシン語を我々が理解して命令するのは非常にめんどくさい。
だから、翻訳してくれるやつを搭載する必要があるのです。(翻訳機能はPCには勝手に入ってます)
翻訳してくれるから、私たちは日本語で検索をしたものを日本語で見ることができるのです。
まとめると
・PCは電気信号によって動く
・電気信号を流す指令は0か1。PCはこの「マシン語」しか理解できない
・だから、PCには翻訳機能が必須
PCを買うとき、CPUのスペック情報が出てきます。
これはざっくりいうと、「どれくらい早く翻訳してくれんの?」てことだと思っていただければと思います。
・「見る人」「仲介する人」「提供する人」
もう少し日常に落とし込んで考えてみましょう。
私たちは、パソコンでYouTubeを見たり、Amazonで買い物をしたり、誰かのブログを見たりすることができます。それは、インターネットを利用して見ることができます。
なぜ見れているのでしょうか?
それを説明していきます。
僕は、このサイトを自分のパソコンを使って開設しています。
それを、違うパソコンで見れるのはなぜでしょうか。
それが、「見る人」「仲介する人」「提供する人」という3つの構造です。
IT用語でいうと「サーバーサイド」と「クライアントサイド」です。
年賀状を例に考えてみましょう。
皆さんが年賀状を書くとき、どのような工程で相手のもとへ届くでしょうか?
まず、年賀状に届けたい住所を書き、ポストに入れます。
運んでくれるのは「郵便局員」です。
つまり「年賀状を書いた人」「年賀状を運ぶ人」「年賀状を受け取る人」が揃って初めて年賀状が届きます。
パソコンのサイトも同じです。
パソコンでの住所は「IPアドレス」と呼ばれるものです。
Webサイトを作るときは、どこかしらのサーバーにIPアドレス(住所)を登録します。
サーバーとは
サーバーとは何でしょうか?
サーバーは、家をイメージしてもらえるとわかりやすいです。
住みたい場所を探して、空きがあればそこに住所登録をする。
それが一戸建ての家だったり、マンションだったり。
サーバーにも色々種類があり、自分で作ることもできるし、どっかのサーバーに登録することもできます。
どちらにせよ、「住む=住所がある」ということです。
それをインターネット上ですると、「サーバーにIPアドレスを登録する」ということになります。
すると、IPアドレスに紐づいたドメインが発行され、みんなが検索できるようになります。
つまり、私たちがインターネットで検索をすると、ものすごい勢いでいろんなサーバーをみにいって、近しい情報を提供してくれます。
これがインターネットの仕組みです。
「サイトを作った人」は、サーバーにサイトを立てる。
「サイトを見たい人」は、サーバーにサイトを見にいく。
仲介がいて、初めて2つが繋がるのです。
・PC動作の連携プレーまとめ
PCがインターネットを使って動作する連携プレーをまとめます。
→電気信号が流れる
→マシン語に変換
→日本語に変換
→検索
→PC動作
→誰かがサーバー上に立てたwebサイトにたどり着く
→サイト情報取得
→自分のPCに戻ってくる
→電気信号が流れる
→マシン語をプログラミング言語に変換
→サイト表示
これが、PC動作の一連の流れです。
細かい部分は置いといて、「あー、だいたいそんな感じね」となっていただけたでしょうか。
小さな理解は新しい興味につながり、だんだん知識が深まっていきます。
もう少し具体的に勉強したい!
という方は、プログラミング教室に通うことをお勧めします。
まずは少しずつ、一歩ずつ勉強していきましょう。