「コミュニケーション」は、どの業界でも欠かすことのできない能力のひとつです。しかし、コミュニケーションと一言でいっても、時と場合によって求められるものは違います。では、様々な場面で求められるコミュニケーション能力とは、具体的にどのようなものがあるのでしょうか?

マナブは、自分でコミュニケーション能力が高いって思う?
うーん、あんまり思わないですかね。


ほう、それはなんでや?
なんか、何言ってるかわかんないって良く言われるんで。


なるほどな(笑)
じゃあ、ワシはコミュニケーション能力高いと思うか?
ツトム先輩は、むちゃくちゃ高いと思います!
言ってること大体納得しちゃうんで。


ぉぉ。ありがとう。
なんか照れるな(〃▽〃)ポッ

じゃあ、マナブにとってコミュニケーション能力が高い人っているのは、「情報伝達能力が高い人」のことを指すんやな。
と、言いますと?


なんていうかな。言ってることが分かりやすい人、ってことや。
あ、そんな感じです。
違うんですか?


うーん、それはコミュニケーションの一要素でしかないと俺は思ってんねや。今日はそのことについて喋ろか。
Contents
コミュニケーションは意思疎通である
コミュニケーションを辞書で調べると、以下のように出てきます。
「意思疎通」とあるように、コミュニケーションは互いに通じあってこそ成り立ちます。そのため、一方的な発信はコミュニケーションとは呼び難いということがわかります。私たちは、落語家、演説家、お笑い芸人などの漫談やエピソードトークを見て「コミュニケーション能力が高い」と表現することがあります。
これこそ、言葉の曖昧さ故に生じる「意味のズレ」です。
まずコミュニケーションをとる上で大切なことは、言葉の意味を理解した上で使えるようになることです。ズレなく会話のキャッチボールができる力。コミュニケーションを行う上で大切なのは、実はこのような単純なことなのです。しかし、意外にもこの単純なことができていない人がほとんどです。その大きな要因は、言葉が抽象性を持っていることです。
ひとつひとつの単語にどういった意味があるのか。どんな場面で使われるのか。今の会話はどの意味で使われたのか。その理解が、コミュニケーションのズレを軽減することに繋がっていくのです。
以下に、言語理解という観点からコミュニケーションに必要な考え方について記載していきます。
抽象→具体
「サバ」
この言葉を見て、皆さんは何を思い浮かべましたか?
「海で泳いでいるサバ」を想像した人もいれば、「料理されたサバ」を想像した人もいるでしょう。
思い浮かべる情景も人によって様々でです。
「海で泳いでいるサバ」と言っても海の中からの目線でサバを想像した人もいれば、水族館のようなガラス張りの場所でサバの群れが泳ぐ情景が思い浮かんだ人もいるかもしれません。料理といっても、刺身をイメージした人もいれば、鯖寿司をイメージした人もいるはずです。
どれも「サバ」であることに変わりはありませんが、ここで重要となるのは「自分が思い浮かべるサバ」と「みんなが思い浮かべるサバ」が同じとは限らない、寧ろズレている可能性が往往にしてあるということです。

なぜこのようなことが起きるのかというと、単語には「抽象性」が存在するからです。
【抽象性】
コトバンク
ありのままの事物を抽象することによって得られる一般的・観念的な性質。
【抽象】
goo辞書
物または表象からある要素・側面・性質をぬきだして把握すること。
海で泳ぐサバも料理されたサバも「サバ」という言葉で表現できるのは、「サバ」の要素を一部抜き出して、一般的な表現として使っているからです。
言葉の抽象性をできるだけ排除するためには、単語を複数結びつけ、具体性をあげるしかありません。
では、単純に具体性を上げると相手に伝わるのでしょうか?
次の例を見てみると、そう単純な話ではないということがわかります。
具体が生むコミュニケーションの弊害

山中さんが昨日ORCAでNA回答のミニマム設定を間違えてさ、実査部が今大変だよ。
急に友人からこんな話をされたと想像してみてください。どう感じるでしょうか?
社会人になると、必要以上に専門用語を使う大人がいます。このような人たちは「専門用語を使うと知的に見える」と思っているのかもしれませんが、冒頭に申し上げたようにコミュニケーションは伝わってこそ意味をなします。
そのため、私たちはTPOで言葉を使い分ける必要があります。
そして、使い分ける必要がある最もたる言葉が「専門用語と固有名詞」です。
固有名詞

例えば、先ほど例にあげた一文。
「山中さん」というのは固有名詞です。
山中さんを話題にあげるなら、お互いがイメージする「山中さん」が同じである必要があります。
「固有名詞」に関しては相手に伝わるかどうかは比較的わかりやすいでしょう。小学校の友達が、自分の会社の上司を知らないなんて考えなくてもわかります。
固有名詞で認識のズレが起きるケースはあまりありませんが、「芸能人」の話をしているときに、相手が別の芸能人を思い浮かべて聞いていたなんてことは、たまにあるかと思います。知っている前提で話を進めていると「あれ、そのドラマ出てたっけ?」「ん?そんな熱愛報道あった?」とだんだん会話が噛み合わずにあとで気づく、ということが私も何度かあります。
単なる世間話であれば笑い話で済みますが、時と場合によってはそれが大ごとになるかもしれません。そうならないために、固有名詞を出して話をするときには会話の冒頭にできるだけ細かく確認作業を入れることをオススメします。

元ジャニーズの手越っているじゃん。newsのメンバーだった。その人についてのことなんだけど……
という感じです。他の人が入り込む可能性を出来るだけ排除して相手にイメージをさせておくことで、会話がスムーズになるはずです。
専門用語

問題なのは「専門用語」です。
とくに同じ業界の人とばかりつるんでいる人は、その業界の言葉が万人に通じるものであり、通じない人は知識不足だと思っている傾向があります。
例えば、先ほど例にあげた一文。
「NA回答」というのは、「ナンバーアンサー」と呼ばれる、マーケティングリサーチ業界では当たり前のように使われる専門用語です。
知識は意識的に取得するものと、環境によって自然と身につくものがあります。私たちが当たり前のように日本語が使えるのは、努力の賜物ではなく自然と身についていったものでしょう。
専門用語を自分の知的アピールのために使っているのか。
それとも相手に伝わっていると思い込んで使っているのか。
前者であるならば、今すぐやめることをオススメします。それは相手にとってストレスであるし、良い印象に繋がらない可能性の方が高いからです。後者であるならば、できるだけ別環境にいる人とたくさん関わりましょう。伝わっているかどうかは、自分ではなかなか気付かないものです。自分が同じような体験を何度も味わったり、人から指摘されることで伝わっていないことに気づくようになります。
地方から出てきた人が、他の出身の人と喋って伝わらない方言があることを知るように、環境の違いが自分の誤認識を教示し、正してくれます。あなたの固定概念を壊し、情報伝達能力をアップさせてくれるのは、あなたの言葉が通じない人なのです。
また、ここでさらに注意すべきなのは、相手がわかっている場合には丁寧すぎる説明はバカにされているように感じてしまうケースもあるということです。
新しいPCを買いにきた若者に対して「ここを押すとパソコンが起動します」「これがマウスで、動かすと画面上の矢印が反応して動きます」というレベル感で説明しないでしょう。
会話の中で相手が分かるレベル感を探ること。
これもひとつのコミュニケーションスキルと言えるでしょう。
言葉の意味を理解する
ここからは、言葉の意味について説明していきます。
言葉には単一の意味しか持たないものもあれば、複数の意味を持つものもあります。
言葉を品詞に分解すると分かりやすいかと思います。
品詞には様々な種類がありますが、ここでは「動詞」「名詞」「形容詞」を取り上げて説明していきます。
動詞

「動詞」というのは、その名の通り「動作」を表す言葉です。
「食べる」「歩く」「話す」「起きる」
動作に対して認識のズレが起きる可能性としては、動作の「範囲」と「レベル感」に対してでしょう。上司に「この資料に目通しといて」と言われ、どのレベルで目を通せば良いのか。
ざっと全体を眺めるだけで良いのか。
それともタイプミスや言葉尻のおかしな箇所があれば指摘するくらいまで一文字一文字しっかり読み込むのか。
これは目的によって変わるため、人から指示された場合は「なぜその作業を行う必要があるのか?」を明確にしましょう。
「これは社内の会議で使う資料ですか?ざっと目を通しておけば良いですかね?」
聞くときは、まず自分で仮説を立て、Yes, Noで答えられる質問をするのがオススメです。もし違うのなら、相当意地の悪い上司でない限り、正しい答えを教えてくれるはずです。
「いや、それは来月導入予定の新システム用に作った取扱説明書で、社外にも公表するやつだから、ミスがないかしっかり目を通してほしい」という具合です。
人は無意識のうちに「これくらいで伝わるだろう」という固定概念に縛られてしまっていると説明しましたが、それは相手も同じです。
「相手は伝えたいことの20%も説明してくれていない」ことを前提に、相手の話を聞きましょう。
形容詞
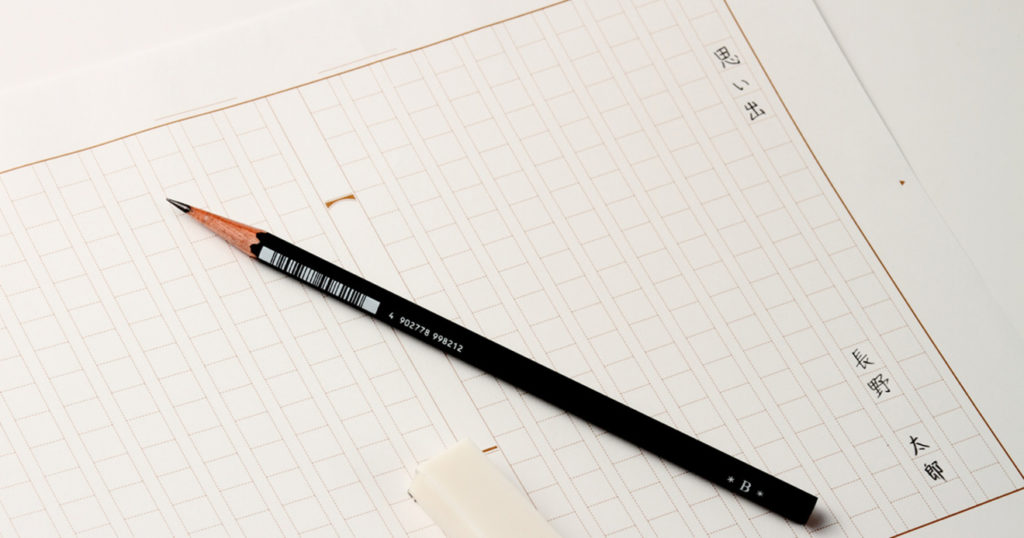
「形容詞」は細かく分けると様々な意味がありますが、ここではざっくりと「状態を表す」とします。
「美しい」「美味しい」「暑い」「楽しい」
状態ですので、英語でいう「be動詞」の後にくるものです。
状態に対して認識のズレが起こる可能性としては、状態の「対象」と「レベル感」に対してでしょう。抽象度が高い分、動詞よりも認識のズレが起きやすい言葉となります。
Youtubeでオリラジのあっちゃんが、こんなエピソードトークをしていました。

学生の時、「時計仕掛けのオレンジ」を観て、むちゃくちゃ衝撃を受けて相方の藤森にオススメした。社会風刺の映画で、当時の自分には映画から感じ取るメッセージが刺激的だった。だから相方に「俺が今まで観た映画の中で過去最高の映画が時計じかけのオレンジだ」と言ったら相方は「あっちゃんがオススメするならむちゃくちゃ良い映画に違いない」と、その映画を初めて付き合った彼女と家で観たらしい。しかし内容はむちゃくちゃバイオレンスで、暴力シーン満載なので彼女にむちゃくちゃキレられたらしい。
これはまさに、「面白い」という認識のズレによって起きた出来事でしょう。
その人の「面白い」と自分の「面白い」が必ずしも一致するとは限らないので、面白さを伝えるのは「どう面白かったのか」という付随情報が重要になります。「行ってみたい」「観てみたい」と感じさせる人の話は、情報からイメージを膨らませることができます。
文章を扱う仕事の人は、出来るだけ形容詞を使わないと言われています。なぜなら、情景が浮かびづらいからです。例えば、「今日はとても寒い日だ」ということを伝えたい時、「とても寒い」だけだとなかなか伝わりません。
「外は呼吸をする度に白い吐息が目の前を覆うほどの気温だ」
「悴んだ手は、手袋をしていてもロクに動かない」
上記の方が、寒さが情景として浮かび上がりやすいでしょう。このように、形容詞は度合いを相手に伝えるために付随情報が必ず必要になります。
「形容詞」は認識のズレがおきやすい。
このことを念頭に入れ、コミュニケーションをとることをオススメします。
名詞

「名詞」は最も固定概念に縛られやすい品詞だと私は思っています。なぜなら、自分と相手の認識が同じだと思いやすいからです。
例えば、友人が「福岡でラーメン屋を始めた」という噂を耳にしたとします。
皆さんは何ラーメンをイメージしますか?
「福岡」というワードから「博多」を連想し、「博多=博多ラーメン=とんこつラーメン」と連想した人がほとんどではないでしょうか?
「連想」できるのは、私たちの強みです。
具体的に説明しなくても、ざっくりした情報でイメージ化できる力が人間には備わっています。そしてそのイメージは、これまでの知識、経験に紐づけられてイメージ化されます。
だからこそ、イメージのズレが生じていることにも気づきにくいという問題があります。
この状態をできるだけ軽減するためには、最初にも取り上げたように「自分が常識だと思っていたことが、他では常識ではない」という、固定概念を壊す経験を何度もすることでしょう。
同じ人とずっと会話しているようでは、コミュニケーションが育つことはないということです。
これからの生き方

ひとつの企業で働き続けるのではなく、複数の企業でステップアップしながら経験値を上げてく。
このような考え方がだんだんと浸透していっているように思います。それは単純に「色んな経験を積む」というだけでなく「凝り固まった固定概念を柔らかくする」という効果もあります。
色々な場面で、人は自分の常識で物事を考えがちです。
「妻だったらこれくらいのことしろよ」
「上司だったらもっと部下のこと考えろよ」
「親だったら」
「政治家なら」
「大人なら…」
コミュニケーションを円滑に進めるためには、多角的視点で物事を見る人間になる必要があります。
グローバルに、様々な人と関われる現代では、多角的視点を持った人材が増え、生きやすい世の中になる可能性は大いにあります。
まずは自分の固定概念を少しずつ知っていくこと。
その一歩目として「言葉の曖昧さからくるコミュニケーションのズレ」をたくさん経験してください。
まずは自分の固定概念を知り、少しずつ壊していくこと。
その一歩目として「言葉の曖昧さからくるコミュニケーションのズレ」をたくさん経験してください。
その経験が、あなたのコミュニケーション能力を向上させてくれるはずです。
「具体と抽象」
著者:細谷功
