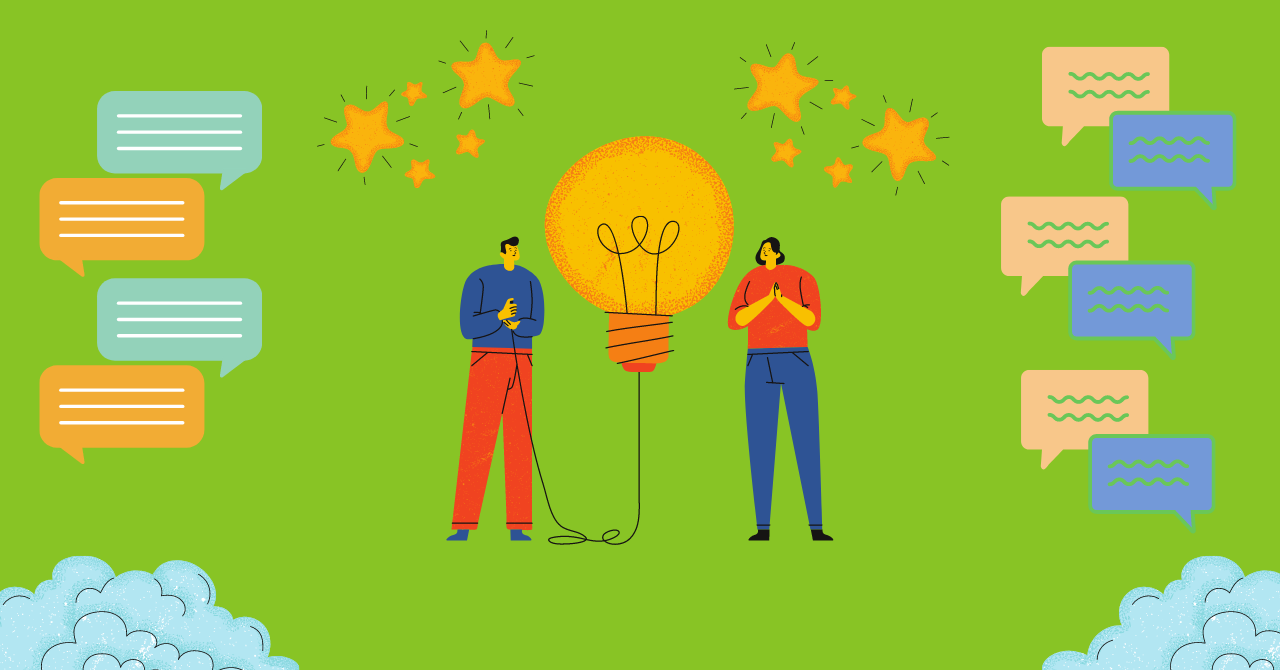平成28年に行われた総務省の社会生活基本調査によると、社会人の平均勉強時間は6分/日という結果が出ています。
しかし、この「勉強時間」はあくまでもアンケートの結果であり、個人が「勉強をした」という認識によるものでしかありません。
私たちは無意識のうちに「勉強=机に向かって参考書を開くこと」のようなイメージを持ってしまっています。それは恐らく、学生時代の学習のほとんどが「講義形式の学習」だったからでしょう。
学ぶとは「机に向かって参考書を開くこと」を指すのでしょうか。
お笑い芸人が、先輩のライブを見に行くことは勉強には含まれないのでしょうか。
プロ野球選手が自分のフォームを撮影して分析することは、勉強として認識されないのでしょうか。
「学習」を大別すると2つに分けることができ、社会に出て役立つ学習は私たちが学校であまりしてこなかったもう一方の学習方法なのです。
日本とアメリカで比較してみると、その違いが分かりやすく表れます。常に経済のトップであり続ける「アメリカ」と比較してみることで、私たちに足りない学習を見出すヒントになるはずです。
「自主学習を進めたいけど、何をして良いかわからない」
「とりあえず本を読んだり、ニュースを見たりしている」
そんな「インプット型」の学びをしている人は、ぜひ読み進めてみてください。
「学ぶ」とは何か、その意味について考えるきっかけになれたら幸いです。
Contents
教育の場~大学の違い~

日本では、大学を「人生最大の夏休み」と皮肉めいた表現をされるほど「自由で楽しい場」としてのイメージがあります。
もちろん大学によって違いはありますし、理系と文系、専攻する学部や所属する研究室によっても違いはありますが、全体的に日本の大学は楽しい場所というイメージがある人がほとんどでしょう。
私の周りにも、大学時代を振り返って「あの頃に戻りたい」とつぶやく人をよく見かけます。私自身、大学の思い出はバイトかサークルのことばかりです。
しかし、アメリカの大学に通っていた学生に話を聞くと、全く別の答えが返ってきます。
アメリカでは大学を「二度と戻りたくない場」と答える人が多いです。
それくらい、日本とアメリカの大学には差があります。
では、日本の大学とアメリカの大学で具体的に何が違うのでしょうか。
入学と卒業の違い

入学の違い
まず、大きく違うのは入学方法です。
日本の大学は大きく「国公立」と「私立」に分けられます。受験方法にも違いがありますが、共通して言えることは「全員が同じような採点方法で判断される」ということです。
【国立大学の入学方法】
- 「センター試験」が必須
- 二次試験もしくはAO入試で採点
【私立大学の入学方法】
- ペーパー試験
- センター利用
- 推薦入試
- AO入試など
私立の方が入学方法のバリエーションは様々ですが、それぞれで「基準」が設けられている場合がほとんどです。そのため、良くも悪くもある一定の「平均点」を超えている人が入学できるような仕組みとなっています。
結果として日本の教育は「平均点を伸ばす」教育が主流です。
平均を大きく下回る分野があれば、補習などで不得意分野を減らすことに時間を費やす。
「全体知識の向上」こそ日本教育なのです。
一方アメリカの場合、大学入学にあたり「学力診断テスト」がありません。
どういった形で入学するかというと、高校での成績や志望理由などのエッセイ、推薦状、スポーツやボランティアなどの活動状況、といったキャラクターの面を重視して選考が行われます。
また、専攻は大学に入学して2年後に決めることになります。
卒業の違い
日本の大学は、基本は4年で卒業(大学院に行く場合6年)となります。
例外もありますが、卒業するには「単位の取得」と「卒業論文の提出」が必要となります。
アメリカも日本同様「単位の取得」によって卒業できます。
しかし、日本以上に単位の取得が厳しく、入学以上に卒業が難しいと言われています。
課題量の違い

日本では、主に「テスト」によって単位が取得できます。
そのため、どれだけ授業をサボっても最後のテストさえ合格できれば単位が取得できる場合がほとんどです。
一方アメリカは、ペーパー試験以外に提出物があり、自主学習の量が非常に多い傾向があります。また、個人課題以外に「グループ課題」があり、能動的にコミュニケーションをとる教育方針となっています。
授業をサボると授業についていけなくなるため、予習をして授業に臨むことが通常となります。
「インプット型」と「アウトプット型」

大学の違いでもわかるように、日本の教育はベースが講義形式です。
単位を取るためには「テストに合格」すればよいため、学生も必然的に知識を詰め込む勉強スタイルになります。
しかし、社会に出るとテストで評価されることはありません。社会に出て評価されるのは「売上」や「成果」であり、それにはアウトプットの力が必要になります。
私たちは、アウトプット力を養う教育をほとんどしてきていません。アメリカのようにディベート形式の授業や正解のない成果物によって判断される評価方式ではないからです。
そのため、私たちは自力でそれらの力を身につける必要があります。
「学校的学習」と「研究者的学習」

インプット型の学習方法を「学校的学習」とするなら、アウトプット型の学習方法を「研究者的学習」と言い換えることができます。
研究者は、目的を達成するために「仮説」と「検証」をひたすら繰り返します。
まず試してみることから始める。
すると、何かしらのフィードバックが返ってきます。
それが自分の望むものと違えば、改善をする必要があります。
「何が悪かったのか?」を分析し
「どうすれば良かったのか?」を考え
「次はこうすれば上手くいくはずだ」という仮説を立てる。
この「仮説」と「検証」の繰り返しこそ、私たちに足りない学習でしょう。
経済は、簡単に言えばお金の循環です。
収益を上げるには、誰かがお金を払ってもらう必要がある。
お金を払ってもらうには、お金を払う価値があると思ってもらう必要がある。
「どうすれば価値があると思ってもらえるのか?」
「そもそも人々は何を求めているのか?」
「今の社会に足りないものは何か?」
それを考え、実践してみることがビジネスです。
私たちが社会で成果を上げるためには、インプットより圧倒的にアウトプットの数が重要なのです。
「パズル型」から「レゴブロック型」へ

経済は、時代とともに進化していきます。
昔は駅の至る所にあった公衆電話は、今やほとんど見ることがありません。
携帯電話の普及により、必要がなくなったからです。
これまでの経済は「パズル」のように正解があるものに対してひたすら作業を重ねていく仕事が主流でした。大量生産大量消費を行うためには、全員が同じ作業を同じレベルでできる必要があったからです。
しかし、それらが機械に代替されるようになった現代では、レゴブロックを積み上げるように正解のない答えを導き出すことに価値が出てくると言われています。
誰にも真似できない、唯一無二の存在になるためにはどうすれば良いのか。
それを考え自己研鑽をすることを求められています。